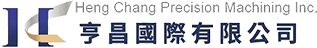- Home
- ものづくりアカデミー
- CNC加工材料はどう選ぶ? ステンレス・アルミ・銅以外にも知っておくべき精密加工でよく使われる金属材料
CNC加工材料はどう選ぶ? ステンレス・アルミ・銅以外にも知っておくべき精密加工でよく使われる金属材料
精密部品の製造において、「材料」は外観やコストだけの問題ではありません。それは加工方法、製品寿命、そして精度安定性を左右する最重要要素です。設計段階での失敗の多くは、寸法の誤りではなく「材料の選定ミス」。
不適切な材料を選ぶと、加工変形、表面粗さの悪化、公差不良などが発生し、最悪の場合は製品全体の不合格につながります。今回は、材料選定の奥深い世界を紐解いていきましょう。
 🔧 材料は設計と加工をつなぐ架け橋
🔧 材料は設計と加工をつなぐ架け橋
CNC旋盤・複合加工において、材料特性は切削速度、工具寿命、加工安定性に直接影響します。
以下に代表的な材料とその特徴を挙げます:
快削鋼(1215、12L14):切削性が良く、コストも低い。量産に最適だが、強度は中程度。
炭素鋼・合金鋼(S45C、SCM440):強度と靭性が高いが、切削抵抗が大きく、剛性の高い機械と冷却管理が必要。
ステンレス鋼(SUS303、SUS316):耐食性に優れるが、切削中に構成刃先が発生しやすく、表面が粗くなりやすい。
アルミ合金(A6061、A5052):軽量で熱伝導性が高く、加工しやすいが、薄肉部品では変形に注意。
銅・黄銅(C1100、C3604):導電性が高く、滑らかに切削できるが、工具への凝着が発生しやすい。
チタン合金(Ti-6Al-4V):高強度・耐食性・軽量性を兼ね備えるが、切削温度が高く、工具摩耗が激しい難削材。
ニッケル基合金(Inconel、Hastelloy):高温・高圧・強酸環境でも安定した性能を維持するが、加工難度は非常に高く、送りや冷却制御が重要。
エンジニアリングプラスチック(POM、PEEK、PTFEなど):軽量で耐摩耗性・絶縁性に優れ、治具や非金属部品に適するが、熱膨張が大きく変形しやすい。
それぞれの材料には一長一短があり、エンジニアは「加工性」「機械的性能」「表面処理との相性」「コスト」を総合的に判断して最適解を導き出す必要があります。
 ⚙️ 材料選定の4つの課題
⚙️ 材料選定の4つの課題
加工性と強度のトレードオフ
硬い材料ほど加工が難しくなります。チタン合金、ニッケル基合金、ステンレス鋼は性能に優れる反面、工具寿命や冷却効率、送り条件の管理が極めて重要です。寸法安定性と変形の制御
一部の材料は切削後、内部応力の開放で変形します。薄肉アルミ部品や熱処理後の鋼材、樹脂部品などは設計段階で補正を考慮する必要があります。表面処理との相性
金属によって電鍍、陽極酸化、熱処理の反応が異なります。アルミは陽極酸化、ステンレスは電解研磨、炭素鋼は亜鉛・ニッケルめっきが適しています。樹脂は研磨やサンドブラストで仕上げ精度を向上させます。コストと供給の安定性
チタン合金やニッケル基合金は高価で納期も長くなりがちです。量産部品では、材料ロットの安定性やトレーサビリティも重要です。
 🔍 材料選定の考え方
🔍 材料選定の考え方
製品開発の初期段階では、設計者と製造側が以下の3点を共同で検討すべきです:
機能性:強度、導電性、耐食性、絶縁性、軽量化のどれを重視するか?
加工性:切削のしやすさ、変形の有無、工具や冷却の要求度は?
後工程の要求:熱処理、めっき、組立、表面仕上げなどの必要性。
設計と製造の両面から最適化することで、「精度・品質・コスト」のバランスを取ることができます。
|