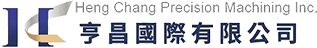- Home
- ものづくりアカデミー
- 部品性能向上のための表面処理とは?防錆・硬化・外観の役割を解説
部品性能向上のための表面処理とは?防錆・硬化・外観の役割を解説
精密加工の分野において、「表面処理」は単なる外観の美化ではなく、部品の性能・寿命・寸法安定性 に大きく関わる重要な工程です。CNC 加工部品の場合、メッキ・酸化・サンドブラスト・塗装などの処理が、前工程の設計や加工条件と適切に連携していなければ、見た目は美しくても、組立て精度・公差・耐食性に問題を引き起こす可能性があります。
 ✨ なぜ表面処理が重要なのか?
✨ なぜ表面処理が重要なのか?
部品表面は、材料と外部環境の「最初の防壁」です。
表面処理によって、以下の特性が向上します。
耐食性(防錆・防酸化)
硬度・耐摩耗性
導電性または絶縁性
潤滑性および外観品質
しかし、処理方法によっては表面の厚み・粗さ・寸法公差が変化します。
前加工段階で十分な加工余裕を設けていない場合、
最終寸法が規格を超えてしまい、組立て不能・隙間過大・機能不良といった問題が発生します。
 🧩 主な表面処理とその特性
🧩 主な表面処理とその特性
| 処理方法 | 厚み変化 | 特徴・用途 | 公差への影響 |
| メッキ | 約 5~25 μm | 防錆・耐摩耗・導電性の向上(ニッケル、クロム、亜鉛、黒ニッケルなど) | 寸法がやや大きくなるため、事前補正が必要 |
| アルマイト処理 | 約 10~30 μm | アルミ材に多用。硬度・耐食性向上、着色可能 | 外層が硬く脆いため、ねじ部や嵌合面には不適 |
| 無電解メッキ | 約 5~15 μm | 均一な被膜で、複雑形状部品にも適用可能 | 均一だが、孔径や公差に影響を与える |
| サンドブラスト | 0 μm(表面改質のみ) | バリ取り・密着性向上・マット仕上げ | 表面粗さが変化するため、嵌合面には非推奨 |
| 塗装/焼付塗装 | 約 20~50 μm | 外観保護や識別用途 | 厚みが大きく、ねじ孔や嵌合部はマスキングが必要 |
 ⚙️ 表面処理と加工公差の重要な関係
⚙️ 表面処理と加工公差の重要な関係
表面処理の厚みは「ミクロン単位」ですが、精密部品にとっては数ミクロンの差が装着可否を左右します。
例えば:
ナットの内径に 15 μm のメッキを施すと、ねじ山が埋まり「ねじが入らない」状態になる。
精密シャフトをアルマイト処理後に研磨しなければ、径が公差範囲を超え、軸受けが固着する。
そのため、設計・加工計画段階で処理厚を考慮し、前加工寸法を調整する必要があります。
 🧠 加工前の「表面処理設計への配慮」
🧠 加工前の「表面処理設計への配慮」
最終品質を安定させるために、設計段階で以下の3ステップを実施しています。
処理厚補正
処理方法に応じて公差中心値を調整(例:外径を小さく、内径を大きく設定)。マスキング設計
ねじ部、嵌合面、接地部などの機能面を保護し、不要な処理を防止。処理後の二次加工
高精度要求部品は、メッキ後に研磨・ポリッシュ加工で寸法を微調整。
 🔍 実例紹介
🔍 実例紹介
ある顧客の精密コネクタ部品(SUS303材)で、黒ニッケルメッキ厚 8~12 μm の指定がありました。
補正なしで加工すると、メッキ後の外径が規格を 0.015 mm 超過します。
そのため、前加工時に -0.010 mm の補正を設定し、
メッキ後に公差中央へ収めることで、スムーズな組立てと均一な外観を実現しました。
このような「寸法余裕設計」は、精密製造における欠かせない専門技術です。
|